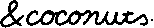「保護犬を迎えたいけれど、実際いくらお金がかかるんだろう?」そんな不安を抱えていませんか?
「保護犬=無料」というイメージを持つ方も少なくありませんが、実際には新しい家族として迎えるための「譲渡費用」や、生活を始めるための「準備費用」が必要です。
この記事では、現役の保護活動支援に携わる視点から、保護犬のお迎えにかかる費用の相場や内訳を徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、お金の不安が解消され、自信を持って新しい家族を迎える準備ができるはずです。
【結論】保護犬のお迎えにかかる費用の総額
まず最初に、お迎え初日までにかかる総額の目安をお伝えします。結論から言うと、一般的には「6万円〜11万円前後」を見ておくと安心です。
| 項目の分類 | 費用の目安 | 内容の詳細 |
| 譲渡費用(団体へ) | 3万〜6万円 | ワクチン、去勢避妊、フィラリア検査等 |
| 初期飼育用品代 | 3万〜5万円 | ケージ、トイレ、リード、フード等 |
| 合計 | 約6万〜11万円 | ※犬の状態や団体により変動します |
ここからは、なぜこの金額になるのか、その具体的な内訳を深く掘り下げていきます。
譲渡費用が必要な「本当の理由」と詳しい内訳
「保護犬は無料だと思っていた」という疑問を持つ方もいるかもしれません。しかし、この費用は「犬の代金」ではありません。これまでその子を守ってきた「医療費や食費の実費」なのです。
代表的な譲渡費用の内訳
・不妊・去勢手術代(2万〜4万円前後)
・各種混合ワクチン(5,000円〜1万円)
・マイクロチップ装着(3,000円〜5,000円)
・フィラリア検査・予防薬(3,000円〜)
・狂犬病予防接種(3,000円前後)
これらの費用を里親様が負担することで、団体はその資金を「次の救助を待つ犬」のために使うことができます。いわば、命を繋ぐための「バトン」のような役割を果たしているのです。
3. 譲渡費用が「20万円」になるケースがあるのはなぜ?
よく見かける「20万円」という数字。譲渡費用としては高額に感じますが、これには明確な理由があります。それは、その子が特別な医療措置を必要とした場合です。
・重度の疾患治療(心臓病や深刻なフィラリア症など)
・交通事故などによる高度な外科手術
・数ヶ月に及ぶ長期の入院加療
これらはすべて「その子の命を繋ぐために実際にかけられた費用」です。金額だけで判断せず、その子がどのような経緯で保護され、どのようなケアを受けてきたのか、そのストーリーに目を向けることが大切です。
お迎え当日から必要な「飼育初期費用」リスト
団体へ支払う費用のほかに、家で準備しておくべきものがあります。最低限必要なものをリストアップしました。
・住まいの準備(1.5万〜2.5万円):ケージ、サークル、ベッド
・食事の準備(3,000円〜):フードボウル、今食べているドッグフード
・お散歩セット(5,000円〜1万円):首輪、リード、ハーネス
・衛生用品(5,000円前後):トイレトレー、シーツ、消臭剤
特に、外の環境に慣れていない保護犬にとって、脱走防止のための頑丈なリードや首輪選びは非常に重要です。
知っておきたい!お迎え後のランニングコスト
初期費用をクリアしても、犬との生活は続きます。中型犬の場合、年間で15万〜20万円程度の維持費がかかると言われています。
毎月の食費だけでなく、毎年の狂犬病予防や混合ワクチン、フィラリア・ノミダニ予防薬など、健康を守るための固定費は必ず発生します。また、将来的な介護や病気に備えた「ペット保険」や「貯金」についても、この機会に検討しておくことをおすすめします。
and coconutsの想い:お買い物が「命を救う」力に
私たち「and coconuts」は、こうした保護犬を取り巻く現実を知り、少しでも力になりたいという想いから誕生しました。
当ブランドの売上の一部は、保護活動団体へ寄付されています。あなたが愛犬のために選んだ一枚のTシャツや散歩バッグが、今まさに救助を待っている犬たちの医療費や食費に変わります。
さらに、保護犬支援アパレル「& coconuts」の商品を購入することも支援の一つです。
売上の一部は保護活動に寄付されており、
あなたの購入したTシャツが、ワンちゃんの未来をつくるかもしれません。
無理のない「お買い物」という形での支援が、一頭でも多くの犬たちの幸せに繋がる。私たちはそんな世界を目指しています。